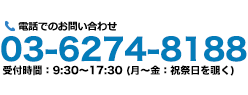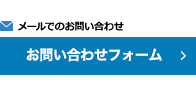税理士による確定申告無料相談所開幕!
私は今年は東京税理士会四谷支部の責任者として
92人の相談担当及び22人の待機担当、
合計114人の税理士による、
公民館等の4会場にて11日間開催の運営を現在しております。
12月から税務署HPや区報などにこの開催の案内が出ております。
課税庁の当該相談所の方針は、予約はネット上のみでの受付とし、
電話の予約を受け付けておりません。
つまり、ネットが使えない方は対象としておりません。
また、スマホ申告のみを対象としたいところなのですが、
まだ課税庁からPCが支給されており、明らかに移行期になっております。
現在使用しているPCは次の更新はしないと発表がされております。
当該無料相談所は課税庁が企画したものに、
東京税理士会が税務支援として有料でお手伝いしているものとなります。
入札して落札した公共事業です。
ただ当該無料相談所の運営は各税務署に一定の裁量があり、
私が責任者を務める東京税理士会四谷支部は、四谷署との事前協議にて
ネット予約のほかに、当日予約がない納税者も受け入れをしております。
どの会場もその当日券を目指して朝から並んでいます。
その多くは70歳超の高齢者で、そのニーズを支部は
把握しておりますので、課税庁の方針に反して当日券で応えているのです。
まぁ~、今までは順調に運営ができておりますが、
これは困るなぁ~っていう納税者も稀にいます。
会社で年末調整をしたのですが、減税分が反映されているのか?
確認したいと・・・・・
私が受付であなたの目的は申告ではないので、
税務署に問い合わせをしてもらえないか?
というと、無料で相談できると書いてあるのに帰れということですか?
相手が税務署職員であると納税者は強く出てきます。
税務署職員が日頃はいかに大変かを知る機会になります。
私はせめての抵抗で、スマホ申告のみを対象としているのを
四谷支部がボランティアでいろいろと受け入れをしていることを理解下さい
と立場を忘れてついつい言い返す時があります。人間ですから。
でも多くの納税者は申告を目的として、事前資料を作成し、
感謝の気持ちを表現して帰られます。
相談担当者もその気持ちを十分感じていると思います。
税理士は独占業務が法律で担保されております。
なので、税務支援が義務付けられています。
社会保険労務士等の士業の先生らにこの業務が解放されれば
税理士会だけでこの業務をすることは無くなります。
税理士業は独占であるから、当該無料相談所に
参加協力しなければならないことを理解すべきです。
私は四谷支部の税理士にそれアナウンスをすることを課題としています。
どこでするのか?なかなかその機会がみつかりません。
無料相談に参加しないということは、
税理士業が解放されればいいと考えているのと同じです。
まぁ~、税理士っていうのは残念ながら全体的に意識が低いのです。
世の中の資格の評価も決して高いものではありません。
でも多くはありませんが、私は真剣に税理士業に
向き合っている先生も知っていますし、
私も税法に正面から向き合ってきました。
この資格の価値を上げたいと常に考えていますし、
税金の分野は税理士のおれだ!という気持ちで常にいます。
いろいろと税理士業については、私には特別なこだわりがあって
独占業務を税務支援の視座からも税理士が守っていきたいと考える者です。
興味があればご照会下さい。
全国対応しています。
租税訴訟補佐人税理士
東京税理士会四谷支部 常任幹事
税務支援対策部部長 水島洋之