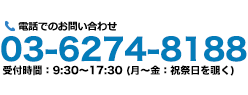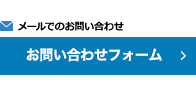以前触れたこのテーマの反響が大きく、
ご意見を頂戴したこともあり、
裁決を再考することにしました。泣
バスの運行費補助金に詳しくなりましたよ。笑
結論から申し上げると、
前回読みこみが不足していた部分として
補助金の額の算定式が一般的な赤字補填方式と
異なっていた点がこの裁決の
肝じゃないかと考えています。
課税庁が更正の請求に対して
「更正をすべき理由がない」としたことが
理解ができたのですが・・・・・私はですが。
一つの路線はバスは市の所有なのでちょっと難しいかな?
もう一つは法人がバス所有して赤字補填方式の補助なので
厳しい判決ではないか?としたのは以前の当方の見解でした。
課税庁が質疑応答事例で
バス路線運行維持補償金は不課税と公表しているのに
それを課税庁が認めないとした一番の理由は
下記にあったと考えます。
ここは審判所が肝としていないので、私はスルーしたのですが
実務家からしたら大きなポイントになるでしょう。
審判所は役務提供と対価の関係を中心に判断しています。
まぁ~、当然なんですけどね。消費税の判断の根幹なので。
ただ役務提供の議論は現場では判断が難しいですよ。
インボイスをみてわかるように、
預りと仮払で原則はプラスマイナスゼロなんですから。
この判断でもある程度は正解が導けます。
今回の大きなポイントは
赤字補填方式が「消費税込」で計算されていたことです。
なかなかないですよ。
全国のバス路線運行費の補助金の要綱をみても・・・・
国土交通省の親分の赤字補填方式が
消費税抜ですから・・・・
裁決事案の市役所が独自の算定方法を採用したってことです。
大概は国土交通省の方式と同じで税抜方式です。
ネットであらかたの公共団体の要綱をみれば出ていますよ。
この時点で役務提供との間の対価って
検討は実務家はしないと思います・・・・
国税庁の質疑応答が若干邪魔しますが、
私なら消費税を認識した収入とします。
だって、理論上、消費税込で赤字を補填されて
これを受給側の法人が消費税の対象外収入で
処理をしたら利益が出ますよ。
そもそも赤字補填が目的なんですから。
こんなことでこの裁決事案は
一般のバス路線運行費の補助金に射程が及ぶものではなく
個別事案裁決であると結論に至りました。
勉強させて頂きました。
何度も判決を読むことで新しい発見があるのも事実です。
興味があればご照会下さい。
バス路線運行費補助金の判定は出来ると思います。
全国対応しています。
租税訴訟補佐人税理士
TaxArtist🄬水島洋之